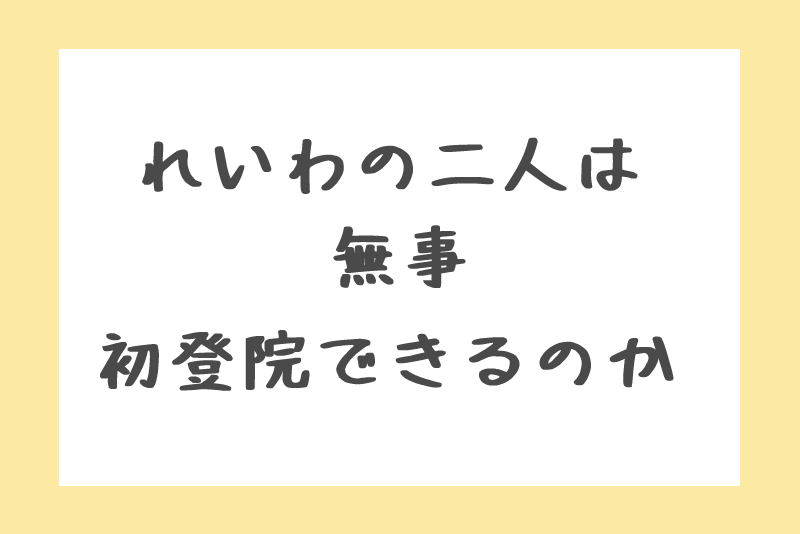選挙が終わり、新しい議員たちが初登院する8月1日の招集日まで、残すところあと数日となった。
「れいわ」のお二人が当選したことで、参議院の受け入れ準備が急ピッチで進んでいる。
先日は、参議院運営委員会のメンバーが二人のもとに出向き、要望などを聞き取りをした。
「何がどう不便なのか」という具体的なことは、経験のない人には分からない。
非常に謙虚で前向きな姿勢で、近ごろめっきり見なくなった中央政府の「良心」を、久々に見た気がした。
思えば、山本太郎氏が木村氏・舩後氏をはじめて公に紹介した時、最初に頭によぎったことは、「彼らになにができるのだろう。」だった。
その時の模様は、こちら
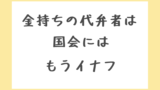
今になって、自分の無知さを恥じる。
彼らの存在は、国会に登院する前から、こうしてすでに国会を動かしつつある。
逆に言えば、初登院前に国会を動かすなんぞ、健常者の議員には出来ないことだ。
スロープや議席スペースの拡大など、物理的なバリアフリーは急ピッチで進んでおり、そうしたことは連日テレビや新聞で報道されている。
しかし、「バリア」というのは、物理的なモノばかりではない。
あえて恥をさらすが、私はバリアフリーと言えば、スロープや段差の解消くらいしか考えたことがなかった。
ところが、彼らが「外に出る」ときには、目に見えないバリアが二重三重にも邪魔をして、できるだけ外に出さないような仕組みになっていることを初めて知った。
重度障害者に対する「重度訪問介護」サービスを国会活動を行っている間も受けられるよう要請した。(略)
重度訪問介護は、身体が不自由などの理由で行動に著しい困難があり、常時介護が必要な障害者に対し、生活全般の支援を行うもの。両氏はこの介護サービスを受けているが、厚労省によると、歳費を受け取る議員活動は経済活動とみなされ、国会に向かうために外出する時点で支援がストップするという。
(2019年07月26日時事通信)
「経済活動」とは、広い意味で仕事を指すのだろう。
議員は「仕事」で、それは収入を伴うので、出かけて仕事をするなら、介護にかかる費用はその仕事で儲けたお金で賄ってくださいね、ということだ。
「仕事をするなら介護は自費で」という制度ルールになっている。
つまりこれは、介護を付けてほしければ、余計なことはせずにウチでじっとしていろ、と言っているのと同じだ。
これは、制度におけるバリアと言える。
彼らが外に出たくても出られない、目に見えないバリアだ。
国民の負託を受けた国会議員が、このような制度のために国会に出向けない、なんてことがあってはならないので、この件に関しても参議院運営委員会は、なんらかの対処をするために知恵を絞るだろう。
運営委には、法を変える権限はないので、なにかトリッキーな法の運用方法を使って、なんとかこの場を切り抜けるのかもしれない。
こうした前例が作られれば、国会ばかりでなく、一般の場での要介護者の「経済活動」も認める方向に話が進む可能性も出てくる。
一連の国会バリアフリーの報道を見ていて心地がいいのは、政権への忖度ではなく、国会議員という肩書がなければ社会で最も弱い存在と言っても過言でない彼らのために、あの国会がいま必死に知恵を絞っていることだ。
これまで、いつも「不安」しか感じさせなかった国会から、久々に届いた「希望」とまで言ったらオーバーだろうか。
と言っても、そういいことばかりでもない。
二人の登場によって可視化されたものは、バリアだけでなく、世間に潜在的に存在する「差別」もそうだ。
それは、障がい者を口汚く罵るタイプのものではなくて、常識的な口調で、道徳性に気を使いながら、丁寧な形で表現される。
言っている本人も、それが差別だとはおそらく思っていない。
そういうものをネットニュースの一般コメント欄などで、多々見かけるようになった。
賛同のクリックも多い。
これは、二人が国会議員になって、初めて姿を現した世間の潜在意識だ。
これまで、必要がなかったからその考えを口に出さなかっただけで、多くの人が「あなたには無理(障がい者なんだから)」「やめておきなさい(障がい者なんだから)」という気持ちを形にしはじめた。
「世間」という悪意のない差別の正体の輪郭が、ようやく姿を現したのだ。
昭和からまるで変わらないこの世間の「潜在意識」を、令和の時代は変えられるだろうか。